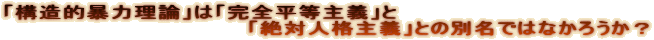|
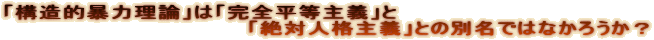 |
|
-「個人レベルの所与」からの解放をも「ポジティブな所与」からの解放をも不可欠としていることに関与して |
|
|
|
西
山 俊 彦 |
|
|
|
“Isn't
Structural Violence Theory Equal with the Principle of Perfect
Egalitarianism and Absolute Personalism
? -Concerning the need to be freed
from both “All the Imputabilities”
attributed to individuals and “All
the Entitlemetns” to what has been given
gratuitously-.”
Research Institute of Christian Culture
Bulletin, Vol. 16, No.1 Mar.2001, pp.153-168. |
|
|
|
要
旨 |
|
J.ガルトゥングの提唱以来、「構造的暴力‐SV‐」の不条理性は汎く受容されてきた。本稿では、その不条理性の根拠を倫理的主体性と法哲学的衡平の見地から、「所与性」にあると同定するが、この究明は責任論・権利論の大転換を促し、人格の尊厳を起点とする正義と秩序を要求する。「SV」理論を、局所的・感傷的抗議の道具に終わらせるのか、或いは、その原理的究明に基いて理論的普遍化・統合を計り、各種秩序の整合的発展を期するのか、「理論」として「SV」理論が使命とする平和と平和学への真の貢献が問われている。 |
|
|
|
|
|
|
|
J.ガルトゥングが提唱した「Structural
Violence ‐SV‐構造的暴力理論」(1)は、すでに社会科学の共有財産であり、理論と実践を展開する豊かな枠組と見做し得る。(2)
筆者は、これ迄に3編を著し、
概念整序化を徹底することによって平和学への貢献を計ってきたが、未だに「SV理論」が[Ⅰ]「完全平等主義」と[Ⅱ]
「絶対人格主義」を基本原理としていることと、その受容と実変化には
[Ⅲ]
関係主体の成熟が不可欠であること、を十分強調したとは言えない。稿を改める所以であるが、依拠する理論は、「事実は規定によって成立する」とする「事実規定論」(3)と論理整合性の徹底、或いは、矛盾律の遵守のみである。 |
|
|
|
[Ⅰ]「SV理論」が「完全平等主義」の別名であること、の根拠と帰結 |
|
|
|
「SV」が無答責
Non-imputable(4)であることの理由は、それが責任能力
Verantwortlichkeit の及ばない「所与 Das Gegebenheit,Hravenly
given((dis-)grace)」であるところに由来するはずであるが、この不条理な所与性を捨象した人間主体には、相互に「完全平等主義でしかあり得ない」という事実が残る。 |
|
|
|
1.「SV」の無答責性の根拠 |
|
人は誰しも、知識と自由をふまえた自らの理性と意思の行使、即ち、責任能力、の及ばない事柄については責任を問われない(5)。「暴力」の定義も「SV」の定義も、それらが責任能力の及ばない(当人にとってネガティヴな)所与であることを示している。 |
|
|
|
(1) 暴力の定義 |
|
ガルトゥングによると「ある人にたいして影響力が行使された結果、彼が現実に肉体的、精神的に現実しえたものが、彼のもつ潜在的実現可能性を下まわった結果、そこには暴力が存在する」(5)と定義付けられる。「実現した現実」が「実現可能性」を下回った場合、そこに暴力が存在した、というのは、文言上は明白だが、実効性は乏しい。なぜなら各人の「実現可能性」は確認しようもないもの、だからである。
隘路打解の方策は、通常、2つある。(1)は、「格差の無条件的想定」であり、(2)は「完全平等の無条件的想定」である。前者(1)は「上手く行った者は能力があったから」「上手く行かなかった者は能力がなかったから」であるとする。根拠を提示しない「現状肯定論」となるが、これは無条件的「結果論」とも「運命論」とも等しくなる。これに対し後者(2)は「誰しも環境に恵まれさえすれば、一定の実現可能性は持合せている」と想定するのであるが、なぜこの想定が正しいのかの根拠は、前者同様、提示しない。筆者の見解は、結果的には後者のそれと似たものとなるが、その理由は別である。筆者によれば、各人の「実現された現実」も「実現されるべきだった可能性」も、同一であっても大差があっても構わない
-いずれも根拠の提示できない想定でしかないのだから-。筆者が問題にするのは「実現された現実」が各人の「責任能力
Verantwortlichkeit」によるものか、或いは、「所与」によるものかという点であって、もし「所与」であるならば、それが暴力であれ生来的才能
innate taleut
であれ、倫理学的にも法哲学的にも無答責であることであった。ガルトゥングと筆者の暴力の定義は、一見、同一であるかのようであるが、ガルトゥングがその現象面を問題にしたのに対し、筆者はその無答責性の根拠を問い、それが「所与性」にある事をもって置き換えることによって、暴力の暴力たる所以を明示しその発展的理解を可能にしている点が重大な相違である。 |
|
|
|
(2) 「SV」の定義 |
|
ガルトゥングによって「Personal
Violence
-PV-個人的暴力」と区別された「SV」は、6特徴をもってする規定と2要件をもってする規定があった。前者は一義的同定の保証されないものであったところから(6)、後者についてのみ検討する。
2要件のよる規定とは「個々人の責任に起因しない」「社会構造に由来する」(7)(13)暴力のことである。今、1997年のGNP,p.c.世界平均が5,130ドル、1996年平均寿命男65年女69年、1995年成人非識字率男21%女38%であるとして、モザンビークの同GNP,p.c.が90ドル、平均寿命男44年女46年、成人非識字率男42%女77%であるとすれば、モザンビークに生を享けた個々人には、経済的・政治的・社会的・文化的…構造に由来する不可抗的な暴力が作用していることは一目瞭然である。そしてこれら構造に由来する不利益の責任が彼らの個々人にある筈がないことは明白だから、責任の由来が(1)「個々人に起因しない」(2)「社会的構造に由来する」と規定された訳である。
ところで、ガルトゥングによる「SV」の規定の最重要のポイントが、その定義に見るように、答責性の如何にあるとすると、(1)「個々人の責任に起因しない」が決定的でこれを指摘するだけでよい筈であるが、たとえ説明的、限定的であるとしても(2)「社会構造が由来する」が不可されちる。しかも、不思議なことに、「構造的」は随所に「個人的」と対比され、通常「社会的」と表現される位置を占めている。確かに、モザンビークの例でみても、「社会的」なものほどその無答責性を理解させ易いことは確かであるが、「構造的暴力」が「社会的暴力」と同義語となるためには、「社会的暴力」以外に「構造的暴力」がない場合である。ところが「身障者として生まれた」とか「家なき児として生まれた」とかは「個人レベル」の事象ではあるが、当人のとっては「責任のない」暴力であり、「社会レベル」の暴力が「構造的」「所与的」で、「社会レベル」の不条理が取り払われねばならないのと同様に「個人レベル」の不条理もとりはらわれねばならない筈である。「構造的」な事象が「社会的レベル」にのみあるのなら「社会的」なる概念は、もともと不用でであったに違いない。「構造的」な事象は「個人レベル」にも存在し、それらを答責如何の観点から整合的に理解できるのは、責任と自由、権利と義務、…の唯一の原点として「人間主体」を据えるかどうかに懸かっているが(8)、その時、「構造的」なる語は「所与的」とならざるを得ないが、その展開と帰結は次節以下に記述する。 |
|
|
|
2.「SV]の無答責性の帰結 |
|
前節では「暴力」と「SV」のていぎを吟味して、「SV」の無答責性の理由が人間主体に対しての「所与性」にあることを立証した。「構造的暴力」という主体に対して「ネガティヴ」な「(社会レベルの)所与性」に確認した訳であるが、そもそも「所与性」は
(1)「社会レベル」にだけ存在して「個人レベル」には存在しないのか、についてと、同じく「所与性」は人間主体にとって
(2)「ネガティヴな事」にのみ存在し、「ポジティヴな事」には存在しないのか、についても検討しておかなければ周到な考察とは言えなくなる。以下の展開の理由である。 |
|
|
|
(1)「社会レベル」の所与性が無答責なら「個人レベル」の所与性も無答責任 |
|
これ迄に「SV」の無答責は、人間主体の責任能力の及ばない「所与性」にあることを立論した。
ガルトゥングの提唱に従って「構造的」=「社会的」であることに異を唱えた者は見当たらないが、一旦、無答責の理由が「所与性」にあるとすると、社会レベルの所与性だけが無答責とみなされていることを再考しなければならなくなる。個人レベルの所与性も限りなく認められるからである。
人は誰しも「誕生」「性別」「両親」「家柄」「地位」「財産」「地域」「国籍」「人種」「文化」等々について特定の“運命”を背負って生き始める。これらが、もし、社会レベルの所与だと言われるなら(9)、「体格」「容姿」「才能」等々の「生来的
innate」所与はどうだろう。これらを、一応、個人レベルの所与として、たとえ個人レベルの事象としても所詮「所与」にすぎず、各人の責任能力の如何ともなし得る事柄ではない。それにも拘らず「個人レベル」に生起する事柄は、あたかも、当人に責任があるかのような差別と偏見が一般化しているのではなかろうか。日本国憲法には「すべて国民は(10)、(所与の如何を問わず)個人として尊重される」(第13条)とか「すべて国民は、法の下に平等であって、
(所与の如何によって)差別されない」(第14条)「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」(第25条)とあるにも拘らず、身障者として生まれついた者が生涯負い目を感じて生きねばならず、高齢者、失職者が切り捨てられて当然とされる風潮は、責任能力の視点から責任権利の基本を弁えぬ逸脱と言わざるを得ない。にも拘らず、偏見を偏見と感ぜず差別を差別として認めない虚無意識が一般社会を支配しているのならまだしも、「社会レベル」における所与性の暴力(不条理)を究明するとする者が、往々にしてより深刻で一般化されている「個人レベル」における所与性の暴力(不条理)を問題視せず、放置しているに等しい現状を何に喩えればよいのだろうか。とにかく所与性は「社会レベル」にも「個人レベル」にも存在する。前者の不条理からの解放の必要性は徐々に浸透してきたかのようであるが、後者の不条理からの解放の必要性は、人権の専門家の間にさえ、一顧だにされていない。前者が無答責なら後者も無答責、前者撤回されねばならないなら、後者も撤回されねばならないのではなかろうか。 |
|
|
|
(2)
(ネガティヴな)所与性について責任なしなら(ポジティヴな)所与性についても権利なし |
|
前項では「社会レベル」の所与からも、それらが責任能力の及ばない所与である限り、何人も等しく責任はなく、その不条理から解放されていなければならないことを見た。これらはネガティブな所与性についての責任如何であったが、ポジティブな所与性についての権利はどうであろうか。ともに所与性として責任・権利能力の及ぶところではないからである。
世にはさまざまなポジティヴな所与が存在する。「社会レベル」では、国土、資源、高生活水準、産業技術、学芸文化等々、所詮、資源大国とか先進諸国の享受するものであるが、「個人レベル」でも、健康、才能、容姿、家柄、財産、等々、多々認められる。これらは、通常、我々の国、私の身体に属するものとして、「我々のもの」「私のもの」とされているのであるが、どのような権原
Berechtigun-
gsgrund でもって私の権利 Das Recht
が発生していると言うのであろう。ネガティヴな所与についての責任能力の発揮如何と同様、ポジティヴな所与についての権利能力
Rechtfähigkeit
が発揮されていれば、権原も権利も発生し得るが、「先進国に生を享けた」もの「素封家御曹司」となったのも、偶有的所与
heavenly given grace
の無償の恵み、でしかなければ、それら所与に対する権限も必然性もあり得ない。筆者は「私的所有権」の不条理性の論証を(11)「自己所有権
Self-Possession,-Ownership」の背理でもって行ったが、」それは、大要次の立論を論駁するものであった。
(1)「自己の身体は自己のもの」であり、(2)「自己の身体の働きも自己のもの」、従って、(3)「自己
身体の働きが生み出したものは自己のもの」(12)
上に記した「自己の身体の働き」を根拠とする「労働取得説」は最も代表的な論証ではあるが、これが成立のためには
(1)「自己の身体は自己のもの」という「自己所有権」が成立していなければならない。ところが「特定の能力を持った身体が私のものである」のは偶有的所与、天与の恵、としか言いようのないもので、先きに「潜在的可能性」の項に述べた通り、「普遍性」「必然性」の裏付けの得られるものではなく(13)、何の権限も主張できない。にも拘らず、「自己所有権」は成立しているかのように見なされ、「私的所有権」は基本的人権の一つとして「資本主義社会の法的基礎」(14)とも「近代国家法の究極原理」(15)とも受容されているが、所詮、既得権益の私物化、持てる者の強権支配にすぎない。「責任能力の行使なくして責任なし」と同様に「権利能力の行使なくして権利なし」であれば、たとえ「ポジティヴな所与」についても「自己所有権」も「私的所有権」も生じていよう筈がないにも拘らず、「ネガティヴな所与」についての答責性を認めない「構造的暴力論」者も「ポジティヴな所与」の独占・排他的支配については異を唱える事はない。体制維持に阿ね、強権支配に奉仕して憚らないのであるが、このような論理整合性に欠ける不条理が、秩序とも正義とも公正とも無縁のものであることは、最早、指摘する迄もなかろう。 |
|
|
|
以上第
[Ⅰ]
章では、「SV」理論の基本原則が「完全平等主義」ではないか、という件について次の順序で検討した。「SV」の無答責性は、ほぼ、受容されているとしても、その根拠が責任能力の及ばない「所与性」にあることは、余りに原理的なことだからか、明確化されているとは言い難い。しかし、一旦「所与性」に無答責性の根拠があるとすると、「社会レベル」の所与性についてだけでなく「個人レベル」の所与性についても無答責となって、ネガティヴな所与に関しては「万人無答責」、即ち、責任について「万人平等」ということになる。同様に「ポジティヴな所与」についても、それが所与であって権利能力の及び得ないものであるところから、何人もその権利を主張できる者はなくなり、ポジティヴな所与についても「万人無権利」、即ち、権利について「万人平等」ということになる。通常「自己のもの」と「権限」「権利」を主張しているものが、所与、天与の恵み(試練)でしかないことがあきらかとなれば、責任(義務)と同様権利においても「万人皆平等」という「完全平等主義」が帰結されることになる。本第
[Ⅰ]
章に展開した原理であったのだが、所与を捨象した処に残る唯一の価値と尊厳が「絶対人格主義」のそれとなることについて、次章に展開しなければならない。 |
|
|
|
[Ⅱ]「SV理論」が「絶対人格主義」の別名であること、の内実と課題 |
|
|
|
前章
[Ⅰ]
章において得られたところは「SV」理論に行きつく先は「完全平等主義」の世界という事であった。何が平等であるかとなると、「所与」による凡ゆる差異差別を捨象した後に残った中心原理、「人格」の平等に他ならない。本章では「絶対人格主義」の世界とはどのような内容を持つ世界であるのかについて、と、そのような世界に経済活動を初め人間活動が、はたして、成立するのか、について考察する。 |
|
|
|
1.「絶対人格主義」の世界 |
|
「所与」に起因する凡ゆる差異差別を捨象した後に残る世界とは、人間主体の世界である。「社会レベル」の所与とも「個人レベル」の所与とも無関係に「人間が、ただ、人間である所以を持って尊重される」とか、「その人が、ただ、その人だからという理由で受容される」ところのものであって、記述のように、「すべての国民は、個人として尊重される」(日本国憲法第13条)と表現されているものにほかならない。
人間主体を認識論的に見れば、「主体的主体」だけが「人格」の名に値する。たとえ人間主体についてであってもそれが認識可能となるのは、「対象化」され「モノ化」されて「自己」(16)とか「客我」(17)となるからであって、それらも認識主体に対しては「所与」と言うしかない。従って「主体としての人格」は具象的描写の対象となるのはおろか、自覚の主体ともなり得ないものである。(18)
存在論的には「人格 Persona」は“Rationalis naturae
individua substantia 理性的本性を備えた独自的主体”(19)というボエチウスの定義が代表的であるが、要するに、それ自体が価値と尊厳を持っている主体であって(20)、「人格の尊厳は相互に比較できないほど崇高で平等とみなすしかないところから、人格の普遍的尊厳は、凡ゆる価値秩序の基準であり目標となる。」(21)決して他の目的実現の手段とはならず、それ自体が目的でなければならない存在であることは、J.マリタンの用いたシェイクスピアの『ロメオとジュリエット』の比喩的表現「
…二人の仲をひきさいている家名を無視して『わたくし自身』を受取ってくださいと訴える、人間の最も内奥の存在」(22)とか、I.カントが“Reich
der Zwecke
目的の国”(23)と命名したものが、ほぼ、これに該当する。しかし、所与を認めず手段を排除する世界に、一体、経済活動を初め人間の営為が成立するのか否かが問われなければならない。以下の設問に幾許かの例示を試みた。 |
|
|
|
2.「絶対人格主義」の課題 |
|
[小問1] 「人格主体」と「所与」との区別は、概念的には、了解可能ではあるが、実態的にはどの
ように識別可能であろうか?
「所与」の多くは可見的であり、その他も了解可能であるから「所与」なのであって、これらが不条理な差異差別の発生源となっているのに対し、主体的主体は、その定義上、意識にさえ上らず、個人と社会の価値と尊厳の根源として想定されているものである。存在論的に両者は了解可能なのだから、認識論的に一方だけが識別できればそれで十分ではなかろうか。 |
|
|
|
[小問2] 所与に起因する事象がすべて無答責・無権利であるのなら、責任・権利能力行使の可能性も
なく、倫理性も主体性も発揮できなくなって、反って人格主義と裏腹の事態を招くことに
なりはしないか?
所与に起因する事象が無答責・無権利である原理は何度も述べた。ところが、別稿でも指摘した通り(24)所与の存在自体に関しては当人にとって所与でしかないが、所与をいかに利用向上させるかは当人の自由と意思に大きく依存し、人格主義にとってはこの領域の方が広大かつ重要なのは明白である。この意味で所与と共に生まれ、自身所与でしかない人間自体は、又、それを超越し、真に支配する使命と可能性を有していることを明記しておかなければならない。 |
|
|
|
[小問3] 多数の社会構成員の中には怠惰で無為に過ごすものが出てきたととしても、それも環境
(所与)のためとされ、罪過を犯した者も同様とすれば、それは「完全平等主義」にも
「絶対人格主義」にも悖るのではないだろうか?
環境の違い同様、勤勉さ、誠実さ、…も多様であれば、怠惰で無為に過ごす者も出てこないとも限らない。しかし、所与の不条理を排除した社会には、人格主義に悖るものが減少すると予測される上に、たとえそれに悖るケースが出てきたとしても、対応原則は、やはり、人格主義のそれであって、各人の厚生が目的であり、そのための支援組織をも整備して、罷り間違っても、“秩序”優先主義に陥ることはあり得ない。 |
|
|
|
[小問4] エゴと打算に応えるところに各自には自力厚生へのインセンティヴが働き、それが経済発
展を促すとすれば、完全「自由」と「平等」の世界には懈怠と停滞だけが残るのではなか
ろうか?
各人には自力厚生へのインセンティヴが、社会全体には何らかの経済発展が必要な事は明らかであるが、要はそれらの動機と目的がエゴと打算のなすままでよいのかという点である。なぜなら、エゴと打算は既得権益の強権支配を肯認し、これを増幅し続けることをよしとするが、本来、経済(・政治・社会……)活動自体は自己目的的ではなく、各人の福祉と共通善の増進に従属奉仕するものだからである(25)。にも拘らず完全「自由」と「平等」の世界には懈怠と停滞が支配すると云々されるのは「エゴ」と「打算」に基いた既得権益の支配を基準とするからであって、「自由」と「平等」を基準とし人格の尊厳の遵守をモットーとする社会には、懈怠と停滞ではなく、「活気」と「張り合い」が支配する筈である。要は、経済活動をその領域だけに終始させることなく、より全体的、より人格的視野にこれを統合させていくことである。 |
|
|
|
[小問5] 所与性については権利も責任もないのであれば、そこにはどんな倫理と秩序が残るのであ
ろうか?
幾度も指摘してきたように、「所与性」からは権利も責任も生じないとすれば、「自由」と「平等」を基準にした「人格」世界はどのような倫理と秩序に基くものかは重要なポイントである。所与性の独占・私物化に由来する凡ゆる差以差別から解放され、自他の区別さえ設けないところから、他者の善を望み実行するもの、自他の関係を普遍的原則(26)でもって自律するものとなる。たとえ、実際的には、外在的に賦課された場合でも、そのないじつが「自由」と「平等」を実現するものであるところから、いかなる「強制」をも「差別」をも伴うものではないところから、かくじんは普遍的倫理秩序の完成に自律的に励むようになる筈である。 |
|
|
|
[小問6] 「所与」の差異にはいかなる権利も責任もなく、権利と責任があり得るのは「人格主体」の
努力だけとなる筈だが、それに基づく配分の差異はどのようなものであろうか?
前問で回答済みとも言えるが、先ず「人格主体」の行為は専ら自発的で自他共愛を原則とすることを忘れてはならない。とは言え「自発性」にも強弱・大小がない訳ではないから、それに基づいた配分の差異迄は否定できないとしても、真の人格世界にあっては妬みと争いの対象ではあり得ない筈であって、「自発性」の「弱小」の主体からは「強大」の主体への反撥が起る筈もなく、他方、「強大」の主体からは「自由」と「平等」の原則の実現を自己の利益に優先させる筈である。そこでは諸他人格とその共通善のために貢献できた事を喜びこそすれ、決して打算と悔恨が先行することはない筈である。 |
|
|
|
[小問7] いかなる社会も法律と組織と文化…なしには成立しない筈であるが、凡ゆる所与を否定す
ることはこれら要件を否定することになりはしないか?
人の誕生も家庭も両親も、言語も民族伝承も、そしてその他の要件も、これらが不可分の所与であることを否定することはできない。しかし所与であることを認めることと、それらが齎すネガティヴ・ポジティヴな効果を容認することは別問題である。本稿の趣旨は、原則として、所与に起因する凡ゆる“暴力”をコントロールすることなしには、正義も人格の尊厳も遵守し得ないという事である。
秩序について一言すれば、その根拠が「自由」と「平等」に基づいていない限りいかほど外的に秩序らしく見えても、その内実は人格主体を侮辱する強権支配と差別に他ならず、早晩、自由と平等を基調とする自律的秩序に代えられねばならないという事である。 |
|
|
|
[最終問] 「所与」の差異には権利も責任も発生せず、「人格主体」は第一義的に権利と責任とも無縁
で、それによる配分も同様とすれば、そこには「完全平等主義」と「絶対人格主義」の世
界が現出するのではなかろうか?
原理的にその通り、しかし、各人の自発性と自律性に基づいて- これが第
[Ⅰ]・第 [Ⅱ]章を通しての結論となる。 |
|
|
|
[Ⅲ] 「完全平等主義」と「完全人格主義」による社会規定には、先ず、同原理 による人間主体の自己規定が前提となること |
|
|
|
第 [Ⅰ]
[Ⅱ]章の展開した「完全平等主義」と「絶対人格主義」の基本原理は、「SV」の不条理性を認めさえすれば、倫理必然的に帰結される論理であった。論理的帰結でさえあれば、直ちに、受容され実効化され行くのだろうか。例をもって語ることを許されたい。
地球上の現人口は61億人、アメリカ人1人1日当りの資源消費量は240㎏、もし全人類がアメリカ人並の生活水準を保とうとすれば「地球は5つ要る」(27)が、それは不可能、アメリカ人並みの生活を送っている者は皆、同世代の人類と次世代以降の人類に無責任極まりない所業を行っている。「生活水準を1/5に切り下げなければならない論理」は明々白々にも拘らず「持続可能な社会」(28)への転換が直ちに行われない理由は何だろう。人間主体が規定する社会的事実は、‟科学的”‟客観的”に明々白々な論理によって自ずと規定されるのではなくて、人間規定主体がそれら論理を論理的と認め、それによって自己を律しようとするところに可能となるからである。この意味で新しい社会的事実の規定は新しい人間主体の規定なしには始まらない-全ての事実規定は規定主体の規定を前提としているのだから-。 |
|
|
|
【註】 |
|
(1)
|
|
J.Galtung,‟Violence,Peace,and
Peace Research.”Journal of Peace Research.Vol.6,№.3,167-191.
高柳先男他訳「暴力、平和、平和研究」『構造的暴力と平和』中央大学出版部、1-66。引用文直後の丸括弧内数字は邦訳
貢。なお彼の著作目録(J.Galtung,Bibliography
1951-1990. PRIO,
Oslo,1990)には、各国語で1,000点を越える論文があると記されているが、それらを渉猟することはできなかった。
|
|
(2)
|
|
高柳先男「訳者あとがき」、J.ガルトゥング『前掲書』、229-232、p.231。
|
|
(3)
|
|
西山俊彦「『もの』の諸相と価値基盤」『サピエンチア』第17号、1983、pp.1-19、他。
|
|
(4)
|
|
‟Imputabilitá è la qualitá e
proprietá delľatto
ed effetto,in forza della quale ľuno e ľaltro vengono attribuiti alľagente come al suo autore e
signore." S.Th.I-Ⅱ, q.21, a.2, Encyclopedia Cattolica.
|
|
(5)
|
|
I.Aertnys・C.Damen, Theologia
Moralis, Tomus I,Marietti,
1956, pp.29-132.
|
|
(6)
|
|
西山俊彦「J.ガルトゥングによる『構造的暴力』概念の整序化と平和への課題」『英知大学キリスト教文化研究所紀要』
第13巻第1号、1998、pp.71-93。
|
|
(7)
|
|
古城利明「SV」、森岡清美他編『新社会学事典』有斐閣、1993、p.433にも。
|
|
(8)
|
|
第2バチカン公会議(1965)『現代世界憲章』中央出版社、1967、12.59.63項. pp.22、98、106。
森村進『権利と人格』創文社、1989。
|
|
(9)
|
|
「個人」と「(集団)社会」各レベルの独自性と拘束性は否定するものではないが、各種事実は未然の混沌から規定主体
が、次元・レベル・観点視点・スパン・時間枠等、各規定枠組によって規定したもの、従って重複、錯視等は当然な事、
但し、「平均寿命」とか「非識字率」のような集計的数値の主体が個々人である事を忘却してはならない。
|
|
(10)
|
|
現代「国家」は、所与性の最大源であるところから、「すべて人間は」でなければ矛盾である。
|
|
(11)
|
|
西山俊彦「私的所有権の不条理性」『平和研究』第24号、1999、pp.100-109、他。
|
|
(12)
|
|
J.ロック(1689)『市民政府論』岩波書店、1968、27.28.29.30項、pp.32-36。
|
|
(13)
|
|
“Nullum
singulare definitur
いかなる個別事象も(普遍的に)規定できない。”Thomas
Aquinatis, S.Th.I, q.29,a.l,ad 1。
|
|
(14)
|
|
渡辺洋三『財産権論』一粒社、1985、pp.8、36、50。
|
|
(15)
|
|
川島武宜『所有権法の理論』岩波書店、1949、p.40。
|
|
(16)
|
|
G.H.ミード(1934)『精神・自我・社会』青木書店、1973。
|
|
(17)
|
|
W.James,Principles
of Psychology, Henry Holt,1890.
|
|
(18)
|
|
中村元「インド思想一般から見た無我夢想」中村元編『自我と無我』平楽寺書店、1968、pp.1-142。
|
|
(19)
|
|
Thomas Aquinatis, S.Th. I, q.29, a.1.
|
|
(20)
|
|
J.マリタン(1947)『公共福祉論』エンデルレ書店、1948。
|
|
(21)
|
|
水波朗「権利の存在論的考察」日本法哲学会編『権利論・法哲学年報』1984、1-25、pp.6-7。
|
|
(22)
|
|
J.マリタン(1947)『公共福祉論』エンデルレ書店、1952、pp.34-35。
松浦一郎「『人格』としての人間」、L.エルダース・奥村一郎編『キリスト教序説Ⅰ』エンデルレ書店、1971、
pp.321-357、355-357。
|
|
(23)
|
|
I.カント(1785)『人倫の形而上学の基礎づけ』『カント全集・第7巻』理想者、1965、pp.81、83、84他。
|
|
(24)
|
|
西山俊彦「前掲論文」1998、p.88。
|
|
(25)
|
|
J.マリタン『前掲書』1952。
|
|
(26)
|
|
I.カント『前掲書』1965、pp.86-87。
|
|
(27)
|
|
NHK教育テレビ「地球白書・第一集・大量消費との決別」2000年10月7日(土)22:00-23:00。
|
|
(28)
|
|
西山俊彦「持続不可能な開発原理の二律排反性と普遍的秩序(平和)構築原理としての不可欠性」『平和研究』第21号、 1996、pp.35-46。
|